1 般若の知恵で仏性を自覚する
禅の経典観1~3までの考察から、『金剛経』にみる禅宗の経典観とは、経典そのものを単に有り難く事物として理解するのではなく、自分自身が生まれ持った仏性を「文字般若」「実相般若」「観照般若」の三つの般若の智慧で自覚するということがわかった。
特に『碧巌録』九十七則「金剛経軽賎」の「垂示」で述べられている「一を拈(と)つて一を放つは、未だ是れ作家(てだれ)ならず。一を挙げて三を明(あか)らむるも、猶お宗旨に乖(そむ)く。直得(たと)い天地陡(にわか)に変じ、四方絶唱し、雷奔り電(いなずま)馳せ、雲行き雨驟(にわか)に、湫(いけ)を傾け嶽(やま)を倒し、甕(かめ)瀉(そそ)ぎ盆傾くも、也(ま)た未だ一半すら提得せざる在(なり)。還(は)た解(よ)く天関を転じ、能く地軸を移す底(もの)有りや。試みに挙(こ)し看ん」(『碧巌録』(下)入矢義高・溝口雄三・末木文美士・伊藤文生訳注、岩波文庫、ニ〇〇一年、二二九頁。)というところでは、経典に書かれている意味を言葉だけで理解するだけでは不十分であることが示唆され、「本則」以降で述べられる禅宗の経典観が一般的なそれと異なることを意味する一文である。
圜悟が「垂示」で、一瞬のうちに得た悟りを再びすぐに手放す自由闊達な働きである「拈一放一」ができたとしても本当の禅僧とは言い難く、また一を言って三を理解する「挙一明三」の鋭い洞察力があってもそれは禅宗の宗旨とも異なり、更には誰もが納得し天と地が逆転するほどの弁舌力があってもまだ半人前の禅僧であると述べているのは、悟りの概念に執着することや言葉を使った真実の伝達の限界に警鐘を鳴らしていると同時に、禅の修行は百尺竿頭に行き着いたとしてもこれまでの修行の成果を全て放下して無にすること、そして悟りは実践されなければ意味がないことを意図している。
そのなかでも特に圜悟が端的に主張したかったことの一つが、教理として認識・認知した禅の内容を実践に結び付けるという「知行合一」ではないだろうか。
2 知行合一
「知行合一」を重んじる禅宗において多くの禅匠たちが禅僧になる決意をした契機は、実際に日常生活で身をもって体験したことが核心となっている場合が多い。例えば、『金剛経』との関係でいえば、先に少しだけ言及した、『五灯会元』巻七「徳山伝」で紹介されている徳山宣鑑(七八二~八六五)が禅僧となった時の逸話が良い一例である。徳山は禅僧になる前は唯識や俱舎などの学問を研究していた学僧で、特に『金剛経』に関しては見識が深く、「周金剛」と呼ばれたほどであった。徳山は『金剛経』で説かれている「金剛のように揺るぎない坐禅と慈悲の智慧をもって、干幼万幼という長い年月をかけて仏の威儀や細行を学んでこそ、ようやく仏に成ることが出来る」という箇所を用いて、「即心即仏」を説いた馬祖道一(七〇九~七八八)の禅を批判していた。
それほど自分の『金剛経』の知識に自信を持っていた徳山はある日、点心を食すため茶屋に立ち寄った時にそこの婆子から「『金剛経』には現在心不可得、現在心不可得、未来心不可得とあるが、あなたはどの心で点心を召し上がるのか」と問われた。しかし徳山はその質問に戸惑い何も答えることができなかった。そんな自分を恥じた徳山は学僧をやめ、禅僧になるために竜潭崇信(生没年不詳)の弟子となることを決意した。
徳山は『金剛経』の「三世心不可得」を通して、どんなに教理的知識があってもその教えが実際に役に立たなければ無意味であることを身を以て知った。この苦い経験が、その後の徳山を修行に没頭させたことは言うまでもない。厳しい修行の末に徳山が知識と体験との一致の自覚を以て悟りを開き、その後に、『金剛経』の注釈書を焼き捨てたのも、文字で書かれた実践の伴わない注釈書が徳山にとって無意味なものと化したからである。この逸話はまさに知行合一の大切さを伝えると同時に、必要なくなれば法すらも捨てることを説いた仏陀の教えを以心伝心している禅僧ならではの行為であることを知らしめている。
以下に簡単に徳山が悟りを開いた話の要約を引用しておく。
龍潭の部屋に入って、師から懇切な教えを聴いていた徳山青年は、時の経つのもすっかり忘れていました。龍潭和尚が、「夜もだいぶ更けたようじや。そろそろ引き上げたらどうじや」と言われたので慇懃(いんぎん)に別れを告げ、簾(すだれ)を上げて外へ出ますと、外は既に真っ暗やみでした。
徳山は戻ってきて恐縮しながら、「暗くて道が分からないのですが」と申し上げると、龍潭和尚がみずから手燭に灯をともして徳山に差し出された。徳山がそれを受け取ろうとすると、龍潭和尚がにわかにその手燭の灯をフッと吹き消してしまわれたのです。そのとたん徳山は忽然(こつねん)として悟りを開いてしまったという話。
(…中略…)
翌日、法堂(はつとう)で説法の時、龍潭和尚が大衆に向かって大いに徳山のことを讃えると、徳山は法堂の前に出て炬火(こか)を振りかざし、「どんなに仏教の教義を究めても、一本の髪の毛を大空に投げたようなもの。世渡りの術を手に入れたとしても、一滴の雫(しずく)を溪谷に落としたようなものに過ぎない」と言って、今まで大事に背負ってきた『金剛経』一に関する論書を焼き払ってしまったのです。(西村惠信『無門関プロムナード』、禅文化研究所、平成十六年、一五一~三頁。)
このような徳山の体験には、『金剛経』が説く「受持読誦とは何か」という問題とその答えが凝縮されており、禅宗における経典のとらえ方を具体的に理解できる内容である。
3 禅宗の経典観の本質は「無功徳」と「忍辱」
この徳山の逸話を含めて今まで考察してきた『金剛経』にみる禅宗の経典観の本質を辿れば、達磨が武帝の仏教への篤い信仰に対して「無功徳」と答えた心境、つまり仏性とは相対差別を越えたところにある「無功徳の功徳」の精神に行き着く。このように禅の教えや逸話では、禅匠たちの悟りの境地が個人的な個性によって千差万別に家風・宗風として表現されるが、最終的には禅宗成立の根本である宗旨に還元される。禅宗が教外別伝、不立文字を標榜する所以がここに見ることができる。
さて、『碧巌録』九十七則「金剛経軽賤」では、禅宗独特の受持読誦や経典の功徳を説くだけに止まらず、忍辱行の大切さを諭していることを忘れてはならない。「若し人に軽賤められなば、是の人は先世の罪業ありて、応に悪道に堕すべきを、今世の人の軽賤むるを以ての故に、先世の罪業は、則ち為に消滅す」という一節を『金剛経』から引用することで、菩薩になるための修行徳目である六波羅蜜、特に忍耐行の重要性を己事究明という禅の第一義からではなく、凡人にも理解しやすくそして実践しやすいように第二義的な立場から説いている。
忍辱行については『金剛経』の「離相寂滅分」第十四にも、仏陀がかつて忍辱仙人となって忍辱の修行を全うしたことで無上菩提を成就したことが述べられている。『金剛経』で布施行と同様に特に忍辱行が強調されるのは、『金剛経』の教えは、順境と逆境といった相対差別するべきものはそもそも世の中に存在し得なく、我相、人相、衆生相、壽相の四相にとらわれない皆空無の相が忍辱行を極めた先にあることを強調しているためだと考えられる。
過去の世に犯した罪業が、この世で屈辱を受けることで、地獄に堕ちずにその罪業が消滅すると言われると、確かに誰でもどんなに苦しいことや嫌なことがあってもそれを耐え忍んでみようという気持ちになるだろうし、それによって仏果菩提へと導かれるのであれば、なおさら忍辱行への志も強くなるに違いない。
教外別伝と不立文字を標榜する禅宗を学術的に考察する場合、誇大妄想とも誤解されるほどの檄文を発する禅特有の表現方法のせいで、どうしてもその解釈や意味の論理性にとらわれてしまいがちになり、それによって禅が示す勘所が不明慮になったり誤解が生じることも少なからずある。それでも所々に「金剛経軽賤」にみられるように、一般的に実践できるようなモチベーションを掲げながら「忍辱行」を説き、人々の苦しみへの救済を差し伸べるところに禅宗ならではの慈悲心を垣間見ることができる。これも禅宗独特の表現方法がもたらす一つの特徴と言えるだろう。
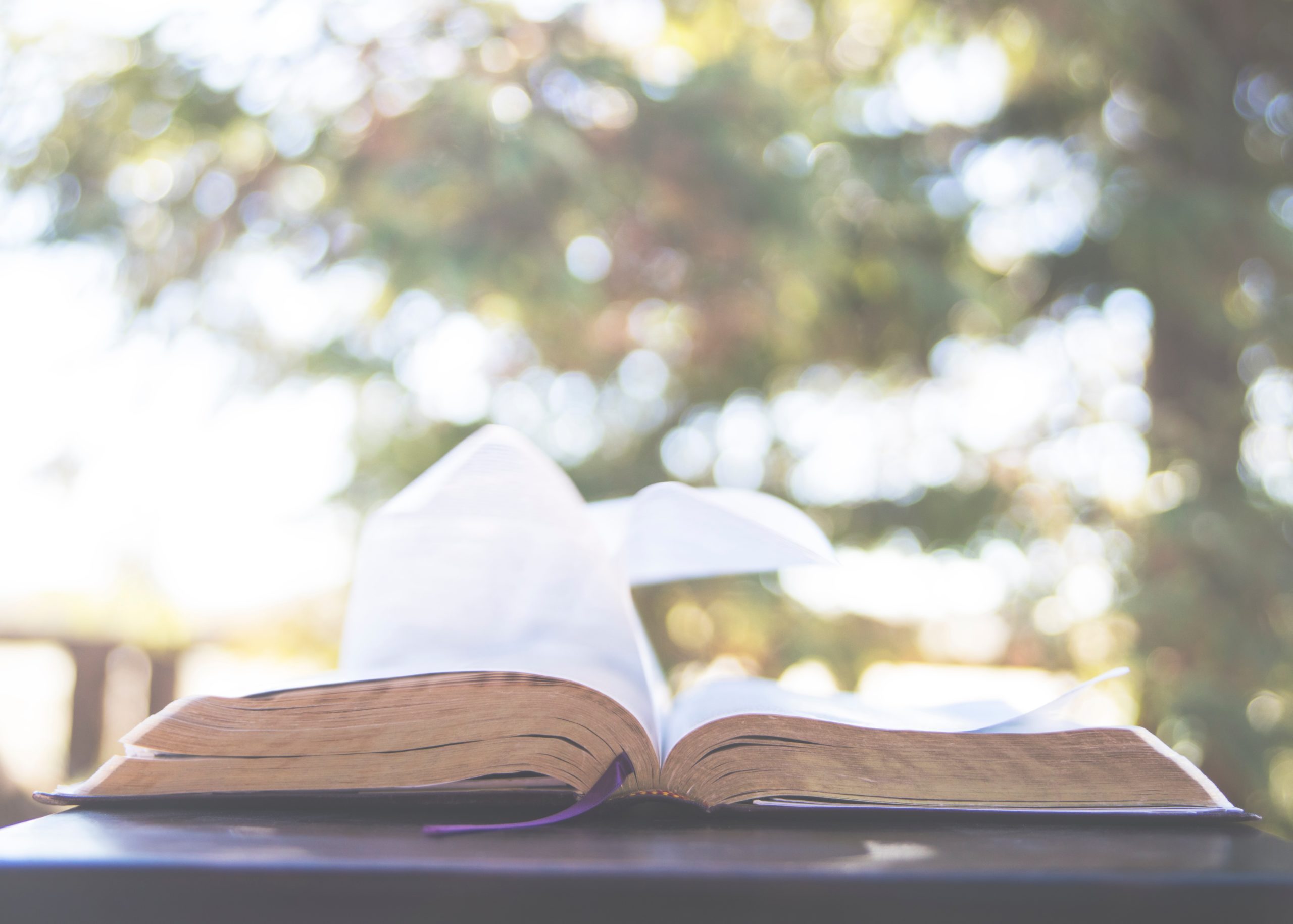





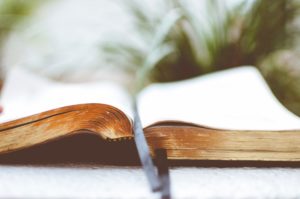

コメント