1 「金剛経軽賤」から読み取る禅宗の経典観
禅宗の経典観1および2で考察した『金剛経』と禅宗の関係そして『金剛経』の教えとその特徴をふまえて、具体的に『碧巌録』「金剛経軽賤」のなかで使われている「此の経」という言葉の意味を明確にしながら、禅宗の経典観に繋がる部分に焦点を絞って、禅宗における経典の受持読誦とその功徳の内容を考察ていこう。
『碧巌録』「金剛経軽賎」の「本則」は、至ってシンプルである。「若し人軽せ賤られなば、是の人は先世の罪業の、応に悪道に堕すべきを、今世の人の軽賤するを以ての故に、先世の罪業は、則ち為に消滅す」、ただこれだけであり、『碧巌録』の他則に見られるような禅僧による独特な問答のやりとりは一切ない。「誰かから侮辱や非難を受けたならば、それはその人が前世で行った悪行のためである。本来ならば地獄、飢餓、畜生の三悪道に堕ちるはずであるところを、この世で侮辱を受けることで前世の罪は消えてなくなる」といった『金剛経』にある経文の一文をただ引用しただけの内容である。
『碧巌録』で取り上げられているこの箇所は『金剛経』「能浄業障分、第十六」の部分であり、ここでは「先世に地獄の業を造(な)すも、善力強きが為に未だ受けず、今世の人の軽賤(はずかし)むるを以ての故に、先世の罪業は、則ち為に消滅す。此の経故(もと)より能く無量劫来の罪業を消して、重を転じて軽と成し、軽を転じて受けざらしめ、復た仏果菩提を得せしむ。教家に拠らば、此の二十餘張の経を転ずるを便ち喚(よ)んで持経と作(な)す。什麼(なん)の交渉(かかわり)か有らん有る底(もの)は道(い)う、「経に自ずから霊験有り」」(『碧巌録』(下)入矢義高・溝口雄三・末木文美士・伊藤文生訳注、岩波文庫、ニ〇〇一年、二三〇~一頁。)と、無尽なる人間の恒沙の罪業を一瞬にして消してしまうことができる『金剛経』の霊妙不可思議な利益が強調されている。『金剛経』を受持読誦さえすれば一瞬にして無限の罪業を消し去ることができる、そうした功徳が『金剛経』にはあると主張している内容が、「能浄業障分」の部分である。
この点について圜悟克勤(一〇六三~一一三五)は「評唱」で、「只だ平常の講究に拠らば、乃ち経中の常論なり。雪竇拈(と)り来(あ)げて這(こ)の意を頌し、教家の鬼窟裏の活計(くらし)を打破せんと欲す」(『碧巌録』(下)入矢義高・溝口雄三・末木文美士・伊藤文生訳注、岩波文庫、ニ〇〇一年、二三〇頁。)と述べ、仏教の教えからすれば至って当たり前の教えである「能浄業障分」の一節を敢えて引用し、言葉で表現された教えのみを頭で理解しようとする「鬼窟裏」と呼ばれる教理家の経典観を否定している雪竇重顕(九八〇~一〇五二)に同意しつつ、教理家とは違った禅宗の経典観を示唆しようとしている。
2 「受持読誦」という意味
そこで次に禅宗の経典観を考察するにあたって、経典の「受持読誦」という意味をどのように理解するかということを考えてみたい。禅宗では教理家が主張するように経典を手にするだけで何か特別な霊験があるという意味での「受持読誦」とは考えない。これは圜悟の「若し恁麼(さよう)ならば、你試みに一巻を閑処に放(ほしいまま)在(お)いて看よ。他(そ)に感応有り也無」(『碧巌録』(下)入矢義高・溝口雄三・末木文美士・伊藤文生訳注、岩波文庫、ニ〇〇一年、二三〇頁。)という言葉に表れている。圜悟は経典そのものには功徳はないということをより詳しく説明するために、具体的に法眼文益、龐居士、そして圭峰宗密の言葉を引用しながら禅宗における「受持読誦」とは何かを説明する。例えば、文益は「仏地を証する者を、此の経を持すと名づく」(同書、同頁)、龐居士は「我聞(がもん)幷に信受(しんじゅ)、総て是れ仮りに名を称す」(同書、二三三頁。)、宗密は「仏地を証する者を、此の経を持すと名づく」(同書、二三四頁。)と受持読誦の意味を解釈している。
では「此の経」とは何を意味するのであろうか。圜悟によれば、「此の経」とは「莫是黄巻赤軸(はたおうかんしゃくじく)の底(もの)、是なりや。且(さて)も定盤星(めもり)を錯(あやま)り認むること莫れ。」(同書、二三一頁。)であって、『金剛経』は単なる「経典」ではなく、「法」や智慧そのものを指し、「法」には「文字」「観照」「実相」の三種類の般若の智慧があると説く。
実際に、圜悟は『金剛経』の「金剛」の意味を「金剛は法に諭う。体堅固なるが故に物壊する能わず、秘用きが故に、能く一切の物を摧く。山に擬すれば則ち山摧け、海に擬すれば則ち海竭く。諭に就いて名を彰す。其の法も亦た然り」(同書、二三一~二頁。)と説明し、『金剛経』の受持読誦とは単なる経典の文字だけを理解することではないと主張している。
もし「此の経」の意味が、『金剛経』に書かれた経典内容を理解することだけであれは、それはあくまで般若とは何か、智慧とは何かについて言葉で説明した「文字般若」を理解しただけに過ぎない。「此の経」という言葉にはそうした「文字般若」に加えて、色も形もないが故に言葉で表現できない意味が含まれている。つまり誰にでも生まれながら備わっている仏性(仏心)そのものであることを悟る「実相般若」、そして二四時間何時でも六根を通じて六塵の世界をはっきり認識し、「実相般若」の具体的な働きである「観照般若」の真智を自覚すること、これこそが「此の経」の意味であり、また受持読誦のことである。
3 経典の功徳
『碧巌録』「金剛経軽賤」では文字般若、観照般若、実相般若の三つの般若の智慧が説明されている。読経や経典の意味を理解すること、ましてや経典そのものには功徳はないとすれば、どんなに経典を各自が手に執って文字般若を有り難く理解しても経典の功徳はもたらされないのであって、むしろ観照般若、実相般若によって真智を悟ることで自分自身が仏であると自覚することこそが、『金剛経』を受持読誦することによってもたらされる功徳である。
『金剛経』の功徳について、圜悟は「古人道く、「人人一巻の経有り」。又た道く、「手に経巻を執らずして、常に是(かく)の如き経を転ず」と。若し此の経の霊験に拠らば、何ぞ止(た)だ重を転じて軽ならしめ、軽を転じて受けざらしむるのみならん。設使(たとい)聖に敵(ひつてき)する功(はた)能(らき)も、未だ奇特と為(せ)ず。」(同書、二三二頁。)と説明し、その功徳の内容を般若の智慧を悟ること、つまり各自がそのまま仏になることだと主張する。
悟りの境地からすればこの功徳はもはや前世の罪が消滅するという狭義を超えて宇宙に存在する全ての真相真理の覚知であり、「大円鏡智」「妙観察知」などに代表される四智そのものを意味すると考えられる。
しかし、そうは言っても『金剛経』では「この法門から四行詩ひとつでもとり出して、他の人々のために教え示し、説いて聞かせる者があるとすれば、こちらの方が、このことのために、いっそう多くの、計りしれず、数えきれない功徳を積むことになる」(『般若心経・金剛般若経』中村元 紀野一義訳注、岩波文庫ワイド版、一九九一年、七五頁。)と説き、「塔廟を供養したり、それに何かを寄進するよりは、経典を読み誦えるほうが、はるかに功徳が多い」(同書、一九九頁。)と、経典の有難さを強調しているところも目立つ。
それにもかかわらず、圜悟が禅宗独自の経典観を示すのは、『金剛経』の中で述べられている経典重視の考えとは反対の側面、つまり教えや法にとらわれてはならないといった「無執着」の思想を強調するためであろう。
圜悟はさらに、『金剛経』を受持した境地について、「明珠は掌(たなごころ)に在り(…中略…)功有る者は賞す。(中略)胡漢(こかん)来たらざれば、(…中略…)全く伎倆無し。(中略)伎倆既に無くして、(中略)波旬(はしゅん)も途を失う。(…中略…)瞿曇(ぐどん)、瞿曇、(…中略…)我を識る也無。(…中略…)復た云く、「勘破(みぬき)了(おお)せり」。」(『碧巌録』(下)入矢義高・溝口雄三・末木文美士・伊藤文生訳注、岩波文庫、ニ〇〇一年、二三六~七頁。)と頌した雪竇に対して、「此の経を持し得て、功験有る者有らば、則ち珠を以て之を賞す。他(かれ)此の珠を得ば、自然に会(よ)く用いん。胡来たれぱ胡現じ、漢来たれば漢現ぜん。万象森羅、縦横に顕現せん。此れは是れ功勲有るなり」(同書、二三七~八頁。)と応えるかたちで、取捨憎愛の分別心を取り去った平等性智、そして事物の持つ機能を十分に発揮する成所作智の境地であることも再度強調している。ここはまさに『金剛経』の重要な主張である「応無所住而生其心」について、わかりやすく解説していると考えることができる。






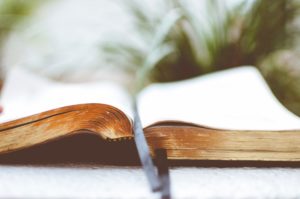

コメント