1 禅宗には経典がない
禅宗は所依の経典を持たない。
仏陀一代経を五時八教と時代区分したなかから、例えば天台宗は、天台大師智顗(五三八~五九七)は『法華経』を仏陀の教えの中で最も円熟した経典であるとし、浄土宗は曇鸞大師(四七六~五四二)によって『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』が撰ばれ、華厳宗は『華厳経』、法相宗は『唯識三十頌』『成唯識論』、三論宗は『中論』『十二門論』、律宗は『四分律』などを所依の経典とした。このように禅宗を除いた中国十三宗はすべて、経典、戒律、論の三論を基盤として立宗開教された。
禅宗が特定の経典に所依しない理由は、初祖達磨大師が中国仏教十三宗の各教祖たちのように五千四十余巻ある一切経から特定の経典を選び、その教えを依用し立宗したのではなく、仏陀が禅定と正覚によって会得した「仏心印」と呼ばれる悟りの智慧のみを伝えたことに起因する。
禅宗が特定の経典を依用しないことについて、『禅源諸詮集都序』上には次のように述べられている。
達磨は法を天竺に受けて、躬(みずか)ら中華に至り、此方の学人の多く未だ法を得ず、唯だ名数(めいすう)を以て解(げ)と為(な)し、事相を以て行と為すのみなるを見て、月は指に在らず、法は是(こ)れ我心なることを知らしめんと欲するが故に、但(た)だ心を以て心を伝うるのみにして、文字を立てざりき。
(鎌田茂雄『禅の語録』9、筑摩書房、一九七一年、四五頁。)
達磨は仏陀による四五年間の説法を記録した経典ではなく、説法内容の根本となる仏心、つまり仏陀の慧命を伝えた。宋の時代に編集された『祖庭事苑』に、達磨が伝えた禅宗の特徴として「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」とあるように、その智慧の根本とは不立文字や教外別伝であり、文字や言葉で伝え説くことはできない。これが禅宗を「仏心宗」と呼ぶ理由であり、また他宗派のような教宗と異なるところである。
2 仏心とは何か
では仏心とは何かと言えば、自分の外に求めて得られるものではなく、自分自身の内に向かって究明していくことによって自覚され得る自性こそが仏心に他ならない。この仏心に目覚めることができれば、誰でも仏になれるという教えが禅宗である。それ故に禅宗は、仏心会得のために経典に書かれてあることを文字上で理解し、経典を有り難いものとして読経することにあまり意味を見出さない。
例えば臨済義玄は経典や読経について、看板に書かれてある単なる文字や便所の紙と同じと述べ、達磨が伝えた禅宗の真意を以下のように強調する。
学人了ぜずして、名句に執するが為に、他(か)の凡聖の名に礙(さ)えらる。所以(ゆえ)に其の道眼を障(さ)えて、分明なることを得ず。祗(た)だ十二分教の如きは、皆な是れ表顕(ひょうけん)の説なり。学者会(え)せずして、便ち表顕の名句上に向(お)いて解(げ)を生ず。皆な是れ依倚(えい)にして、因果に落在し、未だ三界の生死(しょうじ)を免れず。
(『臨濟慧照禪師語錄』朝比奈宗源譯註、岩波文庫、昭和四一年、六〇頁。)
道流、設(たと)い百本の経論を解得(げとく)するも、一箇の無事底(ぶじてい)の阿師(あし)には如(し)かず。你(なんじ)解得すれば、即ち他人を軽蔑す。勝負の修羅、人我(にんが)の無明(むみょう)地獄の業を長ず。善星(ぜんしょう)比丘の如きは、十二分教を解すれども。生身(しょうしん)にして地獄に陥り、大地も容(い)れず。
(『臨濟慧照禪師語錄』朝比奈宗源譯註、岩波文庫、昭和四一年、一二三頁。)
三乗十二分教も、皆な是れ不浄を拭うの故紙なり。仏は是れ幻化の身、祖は是れ老比丘。你は還(は)た是れ娘生(じょうしょう)なりや。你若し仏を求むれば、即ち仏魔に摂(せっ)せられん。你若し祖を求むれば、祖魔に縛(ばく)せられん。你若し求むること有れば皆な苦なり。如かず無事ならんには。
(『臨濟慧照禪師語錄』朝比奈宗源譯註、岩波文庫、昭和四一年、七七頁。)
3 禅宗は逆説的に教えを伝える
禅宗では、どんなに多くの経典を読み、文字や言葉の意味だけでその内容を理解したとしても、仏法は会得できないと説く。禅問答が論理性を欠き、あたかも意味不明な言葉のやり取りを繰り返すのは、言葉の論理性を否定することによって、仏法の不立文字と教外別伝を逆説的に伝えるためである。
では禅宗は全く経典の価値を認めず経典内容を無視するかといえば、決してそうではない。例えば宗門第一の書である『碧巌録』の九十七則「金剛経軽賤」には、不立文字、教外別伝である禅の意味を損なうことなく、禅宗が悟りを得るために如何に経典の存在をとらえるべきかという禅宗の経典観なるものを読み取ることができる。
そこで今回は、『碧巌録』九十七則「金剛経軽賤」を取り上げ、言葉や文字にとらわれてはならないと説く禅宗がどのような経典観を持ち、不立文字・教外別伝を標榜する禅の核心を如何に経典から導き出すことができるかということについて考察してみたい。「金剛経軽賤」を取り上げた理由は、本来特定の経典に所依しない禅宗が、敢えて宗門第一の書である『碧巌録』で『金剛経』を理解するうえでの心得を説くのは、そこに禅の経典観とその在り方の構造が、禅の本質を損なうことなく説明されていると考えたからである。
常識と論理的秩序を看破することで固定概念に縛られることを否定し、「無」の状態から自由で新たな創造を可能とする禅宗の教えを、『金剛経』から読み取るにあたり、まずは禅宗と『金剛経』の関連性、そして禅宗の教えと特徴が垣間見える『金剛経』の部分を明確にし、それらの内容を具体的に『碧巌録』九十七則「金剛経軽賤」と照らし合わせ禅宗の経典観をまとめてみたい。
4 禅宗と金剛経
『金剛経』は大乗経典のなかでも禅宗と最も関係の深い経典とされる。しかし禅宗初期には、禅宗は「楞伽宗」と呼ばれていたことからもわかるように、達磨大師が伝えたとされる『楞伽経』を重んじていた。楞伽宗は『楞伽経』を思想基盤とした初期禅宗教団の異称である。敦煌で新出した『楞伽師獅資記』や『続高僧伝』「僧可伝」「法沖伝」の記述から、初期禅宗と四巻本『楞伽経』との関係が注目され、楞伽宗という呼称が生まれたと考えられる。
『禅の思想辞典』(田上太秀・石井修道編著、東京書籍、二〇〇八年)によれば、『楞伽経』は「自覚聖智の体得を強調しつつ前聖からの伝授を説くなど、禅宗のさまざまな主張のよりどころとなったが、荷沢(かたく)神会(じんね)門下が『楞伽経』を否定して『金剛経般若経』伝授を宣伝し、また禅者の経典離れが進んだ結果、次第に用いられなくなった。」とある。
しかし六祖慧能以降は、『楞伽経』から『金剛経』にその思想基盤を移した。それは慧能が『金剛経』にある「応無所住而生其心」の一句によって大悟したことに始まる。こうして禅の思想は、五祖弘忍まで重視された伝統的な禅定主義を説く『楞伽経』から、六祖慧能以降は『金剛経』の智慧主義へと変わっていった。
「応無所住而生其心」と並んで『金剛経』を象徴する教えが、「過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得」である。この句は公案でも取り上げられるほど、今の禅宗にとっては深い意味を持っている。これについては本論の「むすびにかえて」で論じるので、ここでは詳しく述べないが、簡単にふれておくと、「過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得」の意味が禅を理解するうえで重要となったのは、徳山宣鑑(七八二~八六五)が禅僧になることを決意した時のエピソードに由来する。徳山は自分が今まで学んだ『金剛経』の知識が実践で何の役にも立たなかったことを機に、禅宗が重視する「知行合一」を身を以て知ることになった。
徳山が経験したように、禅宗ではどんなに教理的な知識を学びそれを熟知したとしても、その内容が日常生活で活かされなければ何の意味もないということを常に説く。そうであれば、禅宗における経典の在り方も、経典そのものが有り難いのではなく、経典で述べられている智慧を自ら会得し、その智慧が実生活で常に生かされた「知行合一」の実践があってこそ、禅宗における受持読誦の意味を見出すことができるのではないだろうか。







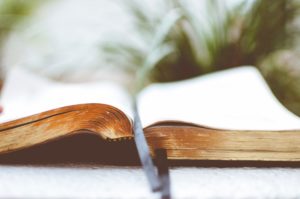
コメント